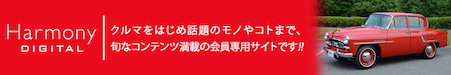過去を思い出し、未来を想像する。人生をより深く味わうための思考の旅へ全4回松任谷正隆のエッセイ 連載Vol.1<過去編>
「カコはミライの中にある」
発表会とポークチョップ

Illustration:Kenji Oguro
僕はあがり症だ。つまり人前に出るのは極めて苦手。なぜなんだろう。いまだに分からない。でも、子どもの頃からそうだった。その最たるものがピアノの発表会で、発表会の数日前から憂鬱は始まり、当日はピークに達した。たいていはお茶の水のYWCAが会場だったのだが、母親に連れられて御茶ノ水駅を降りてからは、歩いていても宙を彷徨うがごとし。目はうつろ。喉はカラカラ。坂を下りながら左手に見えてくるニコライ堂が怖かった。見ないように目を背けた。路地を入って左側にYWCAの入り口はあったはずだ。古い建物で、黒ずんだ木製の建具や、元は白であったはずの壁が黄土色に黄ばんでいる感じとか、とにかくみんな嫌だった。息ができなくなった。
建物の中を少し進むと、もうピアノの音は聴こえていたような記憶がある。もう始まっていたのか?いや、そんなことはない。この記憶は小学校低学年。たぶん1〜2年生だろう。ひょっとしたら早く来た子たちがはじめて弾くピアノで練習をしていたのかもしれない。大きなホールに響くピアノの生音は、それだけで不気味だった。上手い下手ではなく、とにかく大きなホールにいるんだ、ということを認識させられた。いわゆる会場、なるものはここしか知らなかったんだから当然と言えば当然かもしれない。
発表会が始まり、順番が進んでいく。僕の通っていたピアノ教室のメンバーはほぼ女子ばかり。先生が東洋英和女学院のピアノの先生だったから仕方あるまい。それでも男子も数人いた。僕より年下の子もいたかもしれないが、覚えている男子は2人。ひとりは皇室の人。僕より3〜4歳年上だったと思う。もうひとりは大学生で、いわゆるトリを取るような凄腕のピアニストだった。あがり症のくせに、しかも練習嫌いだったくせに、僕の照準はいつもこの大学生に当てていたように思う。なんと身の程知らずな・・・。
とはいえ、僕は年少組ということもあって出番はずっと前。自分の番の3人位前になると客席を出て舞台袖に向かう。不思議なことにこのときの気分はまったく覚えてない。このあと何度も同じ道を通って舞台に行ったはずなのに、一度として記憶がないのだ。そして舞台の下手の袖から何人かの演奏を見るわけだが、子どものことだから、間違えて途中で止まる場合もあるし、なんだかすらすら弾けてしまう子もいた。背中がその子たちの心境を強く物語っていた。僕はなぜか例の大学生よりうまく弾けるイメージを毎回持った。そう、思い込ませていたんだろう。現実逃避だったのか。
前の子が引っ込み、いよいよ自分の出番。最初の一歩はものすごく変な歩き方をした。体が言うことをきかない。照明が当たると(いや、実は最初からついていただけなのだけれど)体がカッと熱くなり、直前にイメージしたものはすべてが吹っ飛んだ。椅子の高さをきっと合わせるのが先だったはずだが、それもあまり記憶にない。覚えているのはピアノの白鍵の黄色さとその象牙模様、黒鍵はなんだか自分の家や先生のところのピアノと違って少し小さく、角が丸かった。それよりなにより鍵盤自体がやたら遠くに見えたこと。椅子をどう合わせていいのか分からなくなった。これも毎回だった。
弾き始める前に、僕は逃げ出したい気分になった。実際、吐きそうだった。ここで吐いたらどうなるんだろう、といつも思った。思うとよけい自分が何をしているんだか分からなくなった。それでも、勇気を出して最初の音を出す。えっ!?と毎回思った。今だから言えるけれど、それは想像と違う音が出るからだ。いや、そうではない。想像などできなかったのだ。会場の残響など、どこの子どもが想像できるものか。しかも、ピアノの鍵盤はどこかガタガタしており、タッチは明らかに違う。出てくる音は全然違う。焦り、自分を見失う。指はピアノを弾いていても実際は何をやっているか分からない。時間は歪み、目が回った。吐きそうを通り越すと、今の自分を俯瞰で見ている自分が見えた。最低だった。まさかここで臨死体験をしたわけじゃあるまい。それでも、それに近い感覚だったと思う。終わったんだか何だかわからないうちにピアノを離れ、一礼をして引っ込む。ああ、逃げたい。もう嫌だ。もうピアノはやめよう。母親に怒られても、もう続けるなんて無理。
客席に戻ると、シャイな母親は褒めるわけもなく、それでも精一杯慰めてくれたんだと思う。
愕然としながら、そのまま客席からトリの大学生のベートーベンを聴いた。ものすごい迫力だった。感情が波打った。ピアノはやめようと思っているはずなのに、なぜか負けん気だけが湧き上がった。
今ならこの一連の感情を自分では説明ができる。もっと言うなら今でも自分は同じだ。人前に出れば同じような感覚に陥るし、吐きそうになることもある。もし、それが少しマシになったとして、その理由をあげるとするなら、それは歳を取ったことだ。自分より年下しかいないんだからいいじゃないか、と開き直れるではないか。
子どもの頃のこういう記憶を傷と呼ぶのだろうか。僕としてはそう呼んでもらいたいところだけれど、きっと世間ではそうは言わないのだろうな。大事な経験とか、そんな言葉で片付けられてしまうのだろう。でもやっぱり傷だ、と思う。傷だから治したいと思うのであって、それだから先に進めたのだと思う。
YWCAを出てすぐのところに小さな洋食屋があった。落ち込んでいる僕は母と2人でここに入り、僕はバカのひとつ覚えみたいにポークチョップを頼んだ。別段おいしい店だとも思わないが、なぜか胃に滲みて涙が出た。
記憶をたどり<過去編>で紡いできた物語から、新たな歩みを描く<未来編>へ――。
次ではこれから先のことを書きます。ご期待ください。

まつとうや・まさたか
◎音楽プロデューサー/エッセイスト。音楽制作にとどまらず、車・ファッションに関する造詣も深く、ライフスタイル系の発信も豊富。