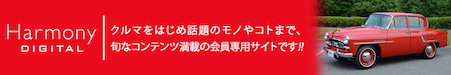自分の「リアル」を信じてシャッターを切るクルマの撮影に情熱を燃やす。カーフォトグラファーというプロフェッショナリズム/河野マルオさんインタビュー

感性と技術の両方が求められる“クルマを撮る”という行為。カーフォトグラファー・河野マルオさんは、自然な目線で光の表情を見極めながら、クルマの本質の魅力に迫る写真を撮りつづけてきました。レンズが捉えるのは「かっこいい」という感情が立ち上がる瞬間。1枚の中古車写真をきっかけに始まったキャリアは、やがて彼を世界の名車が集まるシーンやモータースポーツの現場へと向かわせることに。彼の美意識と哲学に触れながら、クルマを撮ることの奥深さを紐解きます。
Text:Mari Maeda(lefthands)
Photo:Maruo Kono
カーフォトグラファー、河野マルオの視線
クルマを撮るという行為には、卓越した審美眼と感性、そしてスピードが支配する世界でどこを切り取るかを瞬時に判断する直感力が求められます。そのすべてを備えるのが、カーフォトグラファーの河野マルオさん。国産車から海外のスーパーカー、カスタムカー、モータースポーツの現場まで。彼がレンズを向けた瞬間、クルマは「移動手段」を超えた、ひとつのアートに昇華します。
「クルマ自体が、そもそもかっこいいじゃないですか。その時代のトップ企業のトップデザイナーが手がけているんですから。いい光の下に持ってきたら、もう勝手にかっこよく写ってくれるんですよ」
笑顔でそう語る河野さんは、「自然な目線」を大切にしていると言います。極端に目線を下げたりして、無理に迫力を演出するような手法には頼らず、クルマの周りをじっくり歩きながら、「この角度がかっこいいな」と感じたときが、シャッターを切るときだと言うのです。

「それっぽく撮れるからと、安易に煽って撮るようなことはしません。例えば、ボンネットからグリルまでの流れも、自然な目線からの見下ろしじゃないとわかりませんから」
一方、彼の写真には独特の“柔らかさ”があります。理由を聞くと、「僕、乱視なんで」と笑います。
「乱視の目で見た光は、ちょっとハレーションを起こしていて、ほわんとしているんです。その見え方が、自分にとっての“リアル”なんですよ」
そこで河野さんは、あえてレンズを少し曇らせたり、フードを外して光源を大胆に取り込んだりといった手法も取り入れます。

「デジタルカメラでふつうに撮ると、肉眼で見ているよりもきれいに写っちゃう。それをもっと自分の目で見た印象に近づけたくて、工夫しています。以前、レンズに指紋がついたことがあって、そこに光が当たると白っちゃけて見えるのがリアルでいいなって。レンズが汚れたときに、見た感じに近づくということに気づいたんです」
そうして撮る写真は、一見幻想的なようでいて、河野さんにとってはむしろ「自分が見る印象に近い」仕上がりに。その際、景色や光は、クルマの魅力を引き立てるための背景でしかないと言い切ります。

「あくまでも主役はクルマです。クルマの周りはハイキーに撮って、あえて眩しく飛ばしたり、逆に暗く落とすことで車体を浮かび上がらせたりする。情報量が少ない方が、クルマに目線がいくんですよ。それが大事です」
ストリートから世界へ――すべては1枚の写真から
カーフォトグラファーとしてのキャリアの始まりは、意外にも1枚の中古車写真でした。
「中古車屋をやっているスケボー仲間から、『もっとかっこよく撮ってくれたら、もっと売れるかも』って相談されたんです」
参考にしたのは、アメリカのカスタムカー雑誌『DUB』。
「空気感のある写真がかっこいいね、と盛り上がって、雰囲気のある光の感じを意識して撮ってみたら、サイトに載せた翌日に問い合わせが来て、すぐに売れたんです」
そうして撮りつづけていた中古車の写真が、ある日営業担当者の目に留まり、クルマ雑誌の編集者に紹介されることに。走行写真の経験がないまま「サンプルがほしい」と言われ、その夜、さっそく友人のクルマに乗って、夜の街を流し撮り。撮った写真が認められ、カーフォトグラファーとしての道が開けました。

ちょうどその頃、創刊準備中だったモーターカルチャー誌『MOTORHEAD』の立ち上げにも参加。写真の寄稿は、創刊から15年を経た今も続いています。
「それまでの日本のクルマ雑誌って、写真がつまらなくて買ったことがなかったんです。でも、アメリカやドイツの雑誌はめちゃくちゃかっこよかった。自由なんです、撮り方が」
ピントが多少甘くても、動きや熱量が伝わればOK、という感覚。ローライダーが跳ね上がる瞬間や、夜のストリートに浮かび上がる車体の影――そうした写真に宿る「空気感」に、衝撃を受けたといいます。
「流し撮りでフォーカスがブレていても、それがスピード感とか躍動感の表現であればいい。ホイールキャップが斜めでも、それがリアルだからいいんです。日本だと、『ロゴをまっすぐに』とかよく言われるけど、海外では誰もそんなもの気にしません。かっこよければいい、そうじゃないですか?」
以降、自身でもイギリス、フランス、ドイツ、アメリカなど、世界の道とマシンを巡る撮影の日々が始まりました。


「初めから海外のクルマ雑誌に憧れて、めちゃくちゃ自由に撮ったから、それがほかにはない個性として評価されたのかもしれないですね。編集の人たちが、そもそもモーターヘッド(「大のクルマ好き」の意味)でしたから、面白がってくれました」
そう言って、目を細めて笑う河野さん。その自由なマインドと独自の感性から生み出された作品は、やがて自動車メーカーの目にも届くように。トヨタやLEXUSからも声がかかり、SNS用の画像や広告写真、雑誌タイアップの撮影など、活動の場が大きく広がっていきました。今ではクルマだけでなく、ファッションや人物、料理、時計なども得意としています。

「僕が惹かれるのは、その時代の最高の技術者やデザイナーが『これ以上ない』と思って形にしたもの。クルマや時計といったものには、機能を突き詰めた先に生まれた機能美があって、そこに心を動かすエモーショナルなデザインが加わっている。だからこそ、たまらなくかっこいいんですよね」

モーターヘッドたちの聖地で――「夢のような瞬間」をカメラに収めて
海外のラグジュアリーなカースタイルも、ライフワークとして撮りつづけてきた河野さん。中でも、イタリアの名門・ブルガリ家との仕事は特別だったと言います。
「撮影させてもらったのは、ニコラ・ブルガリさん。宝飾ブランドの創業家の一員で、筋金入りのクラシックカーコレクターです」

イタリアでの撮影に始まり、次に訪れたニューヨークでも、垂涎のプライベートコレクションを撮影する機会に恵まれたといいます。
「1週間ほどの撮影が終わると『君たち、美味しいお店があるから、食事をしていきませんか?』と言って、電話をしてくれて。人気の有名イタリアンで、予約困難なのに、行ってみたら満席の店の真ん中のテーブルだけがポツンと空いていて驚きました。食べていたらニコラが現れて『楽しんでますか?』って肩を叩かれて。まるで映画のワンシーンみたいでしたね」
さらにイギリスの名門イベント「グッドウッド・リバイバル・ミーティング」や、カリフォルニアでのクラシックカーの祭典「モントレー・カーウィーク」の取材など、印象深い夢のような話が続きます。数億円のクラシックカーを本気で走らせ、ときにはクラッシュも。一台一台にまつわる歴史と背景をこよなく愛し、「走らせてこそ価値がある」と信じる“モーターヘッド”な人びとに、本物の道楽の粋を感じたと言います。
「クルマの帯びている空気感を感じて、大事にするというのが、大人の趣味ですよね」
さらに、世界のモータースポーツの現場にも出入りし、集中するメカニックの背中や、ピットに漂う緊張感を捉えてきました。

「レースを支える、命がけの舞台裏も伝えたくて。何も知らない人たちが見ても“この世界ヤバい、かっこいい”って思ってもらえるような写真を撮りつづけたいですね」
愛車をかっこよく撮るための5つのヒント――誰でも、スマートフォンでも
最後に、「自分のクルマをかっこよく撮りたい」という読者に向けて、河野さんがアドバイスをくれました。スマートフォンでも、少し意識を変えるだけで写真は大きく変わるそう。
1. 寄って撮る
好きな部分に思いきり寄って。チャームポイントを見つけると、愛も深まります。
2. 主役を明確に
景色も大切ですが、見せたい部分がぼやけると、ただの記念写真になってしまいます。
3. 光の違いを味方に
時間、季節、湿度によっても光は変わります。それにより、同じ場所でも表情が変わるのが面白いところ。
4. 天候に左右されない
「写真は晴れのときだけ」という既成概念を捨てること。曇りや雨の日にはまた独特の質感がでて、むしろ魅力的に撮れることもあります。
5. 好きなように撮る
人真似よりも、自分のフェティシズムを大切に。制約のあるプロよりも、アマチュアの情熱で撮る写真こそ、ピュアでかっこいいのです。
ただの“モノ”を超えたクルマという存在。そこに宿るレガシーや機能美、そして「好き」という気持ちは、写真を通じて必ず伝わってくるはずです。
「かっこよく撮れたときは、やっぱり何より嬉しいですよね」
そう微笑む河野さん。今日もどこかで彼のレンズが、一台のクルマを誰かの憧れに変えていることでしょう。
プロフィール:河野マルオ
河野マルオ(こうの まるお)/クルマを得意とするフォトグラファー。『MOTORHEAD』『GENROQ』『ENGINE』といったクルマ雑誌のほか、『LEXUS NEWS』「moment』でも活躍。トヨタやLEXUSの撮影も数多く手がけている。
https://www.maruokono.info