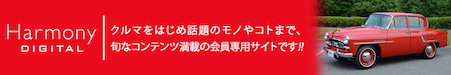気になるトヨタ車守り抜いたこと。変革したこと。
クラウン クロスオーバーの挑戦
文/塩見 智、写真/奥隅圭之、トヨタ自動車、

昨年7月の発表以来、大きな話題を巻き起こしてきたクラウン クロスオーバー。個性的なボディに大径タイヤを履き、4WDレイアウトを備えるこのクルマは、一見伝統的なクラウン像からはみ出した「異端」に見える。
ならばクラウンが守り続けてきた伝統とは、クラウンの本質とはなんなのか? その答えを探しに、クラウンで少年時代を過ごしたモータージャーナリスト、塩見智氏がクラウン クロスオーバーをロングドライブへと連れ出した。
アクセル操作にクルマが即応するダイレクト感

昨年の登場時に取材して以来、約半年ぶりにクラウンクロスオーバーに乗る機会に恵まれた。今回試乗するのは2.4Lターボエンジンを搭載したデュアルブーストハイブリッドのRS、いわゆる“速い方”だ。銀座でキーを受け取り、箱根ターンパイクへ。小田原方面から大観山へ向けて駆け上がった。
最高出力272psを発するエンジンと直列に繋がれたフロントモーターが前輪を駆動し、eAxleというリアモーターが後輪を駆動。前後モーターはそれぞれ最高出力が約80psに達し、システム全体が発する最高出力は349psにおよぶ。これにトルコンレスの6ATが組み合わせられる。
絶対的な力強さもさることながら、このパワートレーンの最大の特徴はダイレクト感だ。アクセル操作に対して即座にクルマが反応してくれる。スポーティーな挙動は山道にうってつけ。楽しい。カメラマンからOKの合図をもらってからも、しばらく走行を続けてしまった。

ダイレクト感はハンドリングからも感じられる。DRS(ダイナミック・リア・ステアリング)によって、低速域では逆位相に、高速域では同位相に後輪が切れるのだが、これが実に違和感なく制御されているのだ。
逆位相の操舵は、ともするとリアが腰砕けになってしまうような気持ち悪さ、いわゆるコーヒーカップ(遊園地の乗り物)フィールをもたらすのだが、クラウンのDRSは介入が自然で、ドライバーが自らの操作によってうまくクルマを曲げたような感覚を保ってくれるため、心地よい。
巻き起こった「クラウン論争」

それにしても、昨年来クラウンに何度も驚かされてきた。
登場前に「どうやらセダンじゃないらしい」「セダンじゃないわけでもなくて、複数のカタチがあるらしい」と驚かされ、歴代モデルがずらりと並べられた発表会では、クロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートの4モデルが鮮烈に披露されて驚かされた。
最初に発売されたクロスオーバーが大径タイヤの装着されたエンジン横置きの4WDであることにも驚かされた。最近のトヨタ車に共通するCシェイプのヘッドランプデザインも斬新だ。

機構もデザインもここまで変わり、予想通り巻き起こったのが、“これはクラウン(としてふさわしいクルマ)かどうか”論争だ。「やっぱりクラウンはセダンじゃないと」「いやクラウンも時代に合わせて変わってよい」「ほかの車名で出てきたらすんなり受け入れられたのに……」など、クラウンオーナー、ファンのみならず、多くのクルマ好きがこぞって自らのクラウン観を語った。
もちろん結論は出ないが、事実としてあるのは、クラウンクロスオーバーは大ヒット中であるということ。
クラウンの歴史は挑戦の歴史だった

保守的な印象を抱かれがちなクラウンだが、実際にはクラウンの歴史は挑戦の歴史、新機軸の歴史といっても過言ではない。観音開きでおなじみの初代(1955年)自体がトヨタの乗用車への挑戦だったわけだが、その7年後に登場した2代目(62年)には、のちのセンチュリーへと繋がる2.6L V8エンジン搭載モデル(クラウンエイト)が存在した。
初代が1.5L直4エンジンを搭載していたことからもわかるように、2代目は国内市場の急成長、急拡大を受けた、トヨタの高級車への挑戦だったのだろう。
ちなみにクラウンが再びV8エンジンを搭載するのは8代目(87年)。海外ではレクサスとして展開した初代セルシオに先鞭をつけた格好だ。センチュリー、セルシオともに失敗が許されないモデルであり、まずは実績のあるクラウンの一部モデルに搭載して様子を見る意味もあったのだろう。

時期は前後するが、3代目(67年)には2ドアハードトップが追加された。以降、81年にソアラが登場するまで、歴代クラウンは2ドアハードトップをラインアップし続ける。エステートを設定した世代もある。
2022年、新型クラウンにクロスオーバー、スポーツ、セダン、エステートの4ボディタイプが設定されることが大々的に発表され、大きな話題を集めたが、昔からクラウンにはさまざまなバリエーションがあった。そのうちのいくつかは、途中で発展的に別の車名を名乗るようになっていったのだ。
アバンギャルドの陰に垣間見える頑固さ

登場以来オーセンティックなデザインが続いたクラウンだが、4代目(1971年)で突如アバンギャルドなデザインをまとって登場した。スピンドルシェイプと呼ばれる丸みを帯びたデザインの4代目は市場で「くじらクラウン」と呼ばれた。
残念ながら販売面で成功したとは言えず、たった3年で5代目へと切り替わった。大胆に変わった現行型は、くじらクラウン以来の見た目の変革と言える。あ、稲妻グリルの14代目(2012年)も印象的だったな。

このほかターボエンジンやスーパーチャージャーエンジンをトヨタ車として初めて搭載したものクラウンだった。つまりクラウンは歴代を通じ、売れ筋モデルでありながら、積極果敢に新技術を投入するエクスペリメンタルなモデルでもあった。
そのいっぽうで、クラウンは初代から一貫してペリメーターフレームシャシーを採用し、91年の9代目で、マジェスタのみにモノコックを採用、次の10代目(95年)でようやく全モデルをモノコック化した。90年代といえば、ほぼすべての乗用車がモノコック化されていた。約40年間、古風なフレームシャシーを使い続ける頑固な一面もあったのは面白い。
変革しながらも乗用車の「中心」にいた

振り返ってみると、クラウンは変わっていないように見え、70年近い歴史のなかで結構変わってきたクルマだとわかる。変革しながら日本の乗用車の中心にあり続けてきたというのがクラウンの本質といえるのかもしれない。
冒頭、クラウンクロスオーバーRSがダイレクトでスポーティーだと書いたが、歴代モデルに通じる挙動も見られた。ソフトな足まわりだ。たとえドライブモードでスポーツ+を選択していても、路面からの入力を一発で収束させるのではなく、ソフトにいなしながら収束させる乗り心地はいつものクラウンだ。

10代の頃、6~8代目が家にあったので、その乗り心地は原体験として身体に染み付いているのでわかる。高い動力性能を考えればもう少し引き締まった乗り心地のほうがバランスが取れていると考える人がいるかもしれない。ただ一から十までスポーティーになってしまっては、それこそクラウンである必要はない。この絶妙な“旦那セッティング”こそが、クラウンをクラウンたらしめているのだ。
新型はメカニズムだけでなく、見た目で新しいユーザーを呼び込み、乗り心地で従来のユーザーを離さないという意味でもハイブリッドクラウンなのだ。
1日の取材を通して、そんなことを感じた。

新型クラウンクロスオーバーを雪道で走って実感!!トヨタの4WDが大進化したキッカケは…WRC!?
自動車評論家、小沢コージさんが語る新型クラウン・GRパーツの魅力
本当に“クラウン”なのか?すべてが変わったクラウン維新を試す
新型クラウンをよりスタイリッシュに彩るMODELLISTAパーツが登場